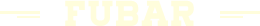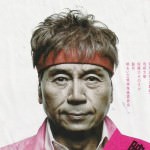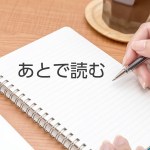デザインをやるときまず押さえるデザインの四原則の話
![]() 2014年6月10日
2014年6月10日
デザインの四原則 – 素晴らしいデザインへの道
機能美という言葉をご存知でしょうか?
日本刀のように切ることだけを目的に作られたものや、F1ののレーシングカーなどある一点の目的に向けて作られたものはそれだけで美しい、機能美を備えております。
つまるところ、僕は最高のデザインの一つでなんじゃないかなぁと思っています。
しかし、これからのお話はこれさえ抑えてデザインすれば最悪でもっぽく見えるというものです。
僕が学生時代に最初の方に教わった考え方でした。
意外と、会社に入ってデザイナーの方がが知らないことにびっくりしましたが、自然と皆身に付けるものなんでしょうね
参考にどうぞ
近接
「近接」とは関連している要素同士は他の関連していない要素より近づけ、関連しない要素は遠ざけるというものです。
これは人間の眼の構造と心理メカニズムに深く関わっています。
人は「カテゴライズ」や「グルーピング」が大好きです。
初めて目にしたものでも、無意識に共通点を見つけて独自の概念を形成します。
あたりまえのことですが、近いものは関連性が高いとなんとなく思ってしまうんです。
この、なんとなくがコンピューターにはできないところなんですが。。。
定食屋さんとか居酒屋さんでこう言う形のメニューとかたまに見ませんか?
上を指しているか下を指しているかわからない。。。
美味しいのに残念だなぁと少し思ってしまいます
整列
「整列」とは見えない線で左揃えや中央などに配置します。
ほぼ全ての要素に当てはまります。
ウェブでいうところのグリッドシステムなんかが代表でしょう。
ほとんどのウェブサイトは見えない線でグリッドが引かれています。
このように左側と真ん中に先が引いてあるようなものです。
デザインをする時一番最初左寄せが一番やりやすいよと教わりました。
その理由は人の目は左上から順にものを見るようになっているからです。
Z型といわれます。
雑誌や、漫画も左上に目立つ物をおいたりコマを持って行ったりします、
ウェブサイトも当初紙媒体のデザインを参考にしていたので左上にロゴ、次に大きめなビジュアルと配置されていました。
今もスタンダードなウェブサイトはこの形式がかなり多いですよね。
しかし、様々なウェブサイトが作られていくうちに最適な目の動きが変化してきました。
紙媒体はページを横からめくるので左から右にめくる場合一番最初に目に入る箇所が左上でしたが、ブラウザは紙のようには表示してくれません。
また、ハイパーリンクの存在など紙とは異なった性質をかなり持っています。
そして、次に登場したのがF型と言われるものです。
左上は変化がありませんがナビゲーションがあることによって一度目線が横にきれます。
その後TwitterやFacebookのタイムラインを表示するサイトが登場したことにより
I型と呼ばれるものが登場しました。
ちょっと脱線しました。
コントラスト
コントラストは複数の要素をはっきりと違わせることです。
いろんな、やり方がありますね。色を変えたり、フォントを変えたり、大きさを変えたり
などなど、コントラストは奥が深く色々試してみると引き出しが増えそうです。
反復
「反復」はそのデザインの中で繰り返し使うルールのようなものです。
ベタなのは見出しとかですかね。
ただ漫然と使うのではなくページ、制作物を統一するように使用することが効果的です。
大きさや、色を繰り返すだけでなくテイストも反復するとより一貫性が生まれ説得力につながります。